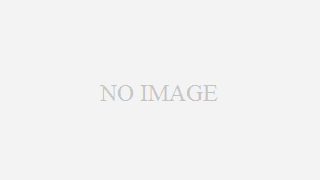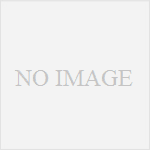Debate Noam Chomsky & Michel Foucault – On human nature [Subtitled] – YouTube
もし仮にフーコーの言うコンセプト性がすべてに当てはまるのであれば、チョムスキーの言うような反論は十分考えられる。フーコーの論理によれば、全体的な集合物である、軍隊や警察や大学を始めとする機関は愛や友情と言ったような理想的なものは持ちえないはずである。だがこの論理は間違っているとチョムスキーは指摘する。なぜならば全体的な集合物である、こういった機関が成り立つ過程において、それ自身が個々人の集合性を求めるのであれば、そういった個々人にも当てはまる論理はコンセプトのみなはずであり、そこに愛や友情といったものはないはずである。だがしかし、我々は日々の生活の中で、愛を育み妻や夫を求め子供を持っている。そして、生活の中で友情を培い、友人を持っている。個々人のレベルとそれらが構成する機関のレベルとでも同じ論理が成立するはずであるが、頑としてそうではないことを我々は生活というミクロの世界の中で事実、知っているのである(現に配偶者を持ち子供を持ち友人を持っていることを我々は日々実感しながらそれに満足する)。ゆえに、日々の生活の中ミクロな世界で論理が成り立つのであれば、先だって挙げた各種機関でも同じはずだ、というのがチョムスキーの反論である。とすると、フーコーの論理は間違っているはずである(事実、チョムスキーはそう言っている)。なぜだろうか?
一方でフーコーはこう答える。我々市井の人々が知っているように大学を始めとする高等教育機関は、知識を授け、多くの人々の生活を豊かにするがため存在している。しかしながら、その教育的機関は、権利を、知識を授けるのにかかわらず、それ以外の定員から排除された人々を苦しめるような作用を持つ。軍隊も警察も同じである。なぜならば、軍隊や警察は国家や地域の治安を守り、多くの人々に恩恵を授けようとする教育機関とほぼ同等の論理をもつからである。しかしながら、それに従えず、また従わなかった人々を排除し、罰する。すると、これらの人々は社会からパージされるわけである。フーコーによれば、そういった人々を救うためにまず、コンセプトたる機関主義を否定し、これを徹底的に攻撃しこき下ろすことで、仮面が外れる(unmasked)とし、そのとき初めて人々は機関主義と向き合えるという。これが人間の本性の大本の根っこである、とした。
現に毛沢東は人間の本性を区別し失敗している。またソ連でも同じである。人間の本性はプロレタリアートとブルジョワジーに区別でき、その間の闘争の中で、プロレタリアートが勝利し、ブルジョワ的資本主義を否定することで革命は成立する、そのときに理想的な社会主義的社会が成り立つのである。しかしながら、毛沢東支配下の中国でもソ連でも同じ現象が起きた。というのも、そもそも彼の言う人間の本性の区別に従い、プロレタリアートが勝利するのであれば、間違った社会形成の方向へ我々は向かわないはずである。しかしながら、毛沢東は社会主義的な理想像を追い求め、文化大革命を断交し、多くのブルジョワジーを否定し虐殺し、人間の本性を区別しようとして、プロレタリアートとブルジョワジーによる闘争を行おうとしたが、結果的にはブルジョワを中華世界から抹殺し、プロレタリアートも救われなかった。ソ連でも同じである。ゆえにソ連は崩壊した。つまり、「毛主義」は人間の本性の悪性さを晒しだしたに過ぎなかった。フーコーは間違った方向へ向く思想として、そういった自由創造的な社会あるいは人間の本性の定義が危険すぎることを指摘したわけだ。
ほぼ時同じくして三島由紀夫もまた似たようなことを言っている。知識というものを授け学問に力があるということに反感を覚えざるを得なかったと彼は言っていた。そういう意味で、右翼である三島が全共闘を一定程度評価したのは合点がいく。なぜならば、全共闘は(三島も嫌うような…)戦後知識人の鼻頭を徹底的にかち割ったからである。それを三島は、戦後左翼学生団体の「功績」として認めた。
つまるところフーコーの言うこともチョムスキーの言うことも間違ってはなく、そこに大きな隔たりがあるとすれば、作家的な主観と客観の違いである。フーコーは見る人だが、チョムスキーは生成文法をはじめとして創る人だった。三島はその両感覚を覚えた稀有な天才的作家であった。そしてそこには主観なき客観はありえないとするヤスパースの論理が中立的にあるように感じる。しかしながら、フーコーおよびチョムスキーのその思想的な立場上、対談は入門向けに収まっている。それがフーコーとチョムスキーの対談のおおよその限界点であり、誰にも打ち破れない壁であった。