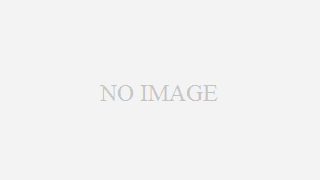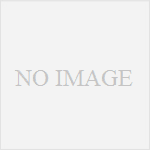「WASarD」の問題提起
先日、「WASarD」のデモ版をやっていて気が付いたこと。このゲームって、シングルスティックシューティングゲームを謳ってるんだよね。んで、気が付いたことをまとめてみよっかな、と。今回はそんなゲームの設計手法に関する記事です。操作量が少ないシングルスティックとは?一体どこが魅力的なのか?今後、操作量の問題をゲーム上で考えるとなると、開発においてどういった問題提起ができるんだろか?
ツインスティックではなくシングルスティック
シングルスティックっていうからそもそもどういうゲームなんだって思うやん?ふつーツインスティックシューってのがスタンダードで、これまでシングルスティックシューなんかは聞いたこともない、って思うやん?このゲームね、プレイヤーができる操作が自機の移動だけなんだよね。つまりAimとShootの概念は完全にオートマチックになっている。面白いところに気が付いたなって思う。これだけ淡白なゲーム操作しかできんとすると、内容も淡白なんじゃね?って思うだろ?全然そんなことないんだよねw
「Vampire Survivors」という始祖
確かにこのゲームがこの分野の始祖ではない、というのもわかる。かねてより傑作の誉れが高いシングルスティックシューである「Vampire Survivors」にも同じような設計方法があるからだ。共通してるのは、あえてプレイヤーがマネジメントできる操作量自体をかなり下げている・意図的に少なくしているってところだよな。これがゲームとして強いのか?というと基本的には弱いと思う。操作量を少なくするということはゲームのインタラクティブな面を一定程度否定するってことだからだな。
「Enter The Gungeon」に近いゲーム性
でも工夫次第で操作量が低い~例えば、ツインスティックよりもシングルスティックのほうが~面白味を担保できるっていう要素もあると思うんだ。現に「Vampire Survivors」は間違いなく面白いし、その影響下で作られた「いっき団結」も面白い。そして出てきたのが今回の「WASarD」。このゲームは「Vampire Survivors」系のゲームと違って、ルームクリア型のゲームなんすよ。ありていに言うと、傑作「Enter The Gungeon」に近い。
インタラクティブ性をあえて低下させる
ルームをクリアして行って、次のルームに移る。スペルアイテムなどを取りながら最深部のボスに挑む。これだけのゲームでも「Enter The Gungeon」は間違いなく傑作だった。やってて楽しいじゃん。緊迫感があって、限られたリソースの中でアクション性に優れたゲーム体現を地で行く。さらにシンプルにしたのが「WASarD」なわけだ。つまりスティックの片っぽだけで操作できるようにゲーム要素を次元削減しているのが「WASarD」なのだ。だが、それは悪いことなんだろうか?問題はインタラクティブ性が低下したから悪いのだろうか?っていうことなんだよね。
AutoAim兼AutoShoot
実際、このゲームやってみたけどマジで面白いんだよ。ツインではないシングルスティックなところがミソよね。AutoAimかつAutoShootにして、操作量だけは当然減ってるよ?その分、ゲームからゲーマ側への要求は事実減っているんだわ。それが直感的な操作が可能になっている、っていうこと。ゲームにスムーズに入れて、理解の壁も低い。簡単なんだよな、ゲームシステムが。あえて語弊を承知で言うけど、隻腕(広く言えば、身体障がいを抱えているかたたち)のゲーマでもプレイが可能。これって興味深い設計だよな。アクセシビリティっていうのかねえ。つまり、操作量を減らしたから、つまらんゲームになった、とかインタラクティブ性が薄まった、って定型的には言えない別な面もあるんだよな。
ゲームそのものにフォーカスすること
むしろ、次元を削減し・操作量を削減したからこそできるゲーム表現ってのも重々あるんだ。前述したように、ストレッサーが減るから、ゲームペースを維持しやすくなるし、その分ワンプレイワンプレイに対する集中力も高まる。プレイの質が高いゲームがトレース可能になるんだよな。つまり、単純にインタラクティブ性を増そうとして、ゲームコンテンツやゲームシステムを複雑化させたり交絡化させたりすることとは別のベクトルでもゲーム制作の哲学はあっていいってことを、このゲーム「WASarD」は示していると思うな。
複雑化に対する工夫
たぶん、ゲームをより楽しませたいならば、複雑なゲームシステムの中で、より交絡化した理解力を求めるゲームデヴェロッパが多いと思うんだ。その究極系がCivでありHoIであるってことにあんまり異論は呈せないだろうな。究極のゲームだからさ。でもね、その逆のソリューションもある、っていうことは、ゲーム開発に携わる人としては忘れちゃいけない、ってことを示しているよね。複雑なゲームのシステムは当然ゲーム史の歴史を辿ればいくらでも見つかるだろう。だが、その逆のベクトルを向いた、前時代的なゲームが新しい表現を作るっていう面も忘れてはならない。あっていいことなんだよ。なんつか、温故知新っていうのかねwゲームシステムが一見退化したようでもそれがホンマ・モノホンの真実だとは限らないんだよな!
秀才は複雑な事象をより複雑な方程式で定義しようとする。
一方、天才はそうした複雑な事象を極めて簡単な方程式で定義しようとする。