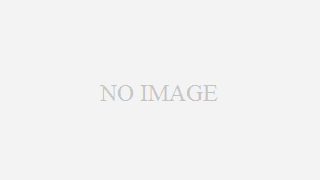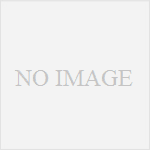記事の要約:ニール・ゲイマン独自のホラー作風の児童青年文学的応用となっている作品。”謎に対する考察”・”人物の持つ真価”・そして”フロイト流の悪魔”を感じさせる出来。この中で現代的価値がいまだにあるのは、”人物の持つ真価”という『人間による価値判断と成長におけるその位置付け』にこそあると個人的には感じた。

ゲイマン流のゴシックホラー(といって差し支えないのかはわからんが)の色彩が深く出ており、また、彼自身が描く”物語あるいは現実のどこに潜んでいるのかわからない闇の部分”をきっちり描いた作風の青年小説。原作は「サンドマン」で有名なニール・ゲイマンです(原著「コラライン」は2002年の作品)。
全編を通じて、謎が多いんですね。考察が大分多くなされているのも納得するほどです。例えば、ボタンの魔女の正体はなにか?とか、あるいはもう一つの家の世界での協力者はなぜ積極的にコララインを助けるのか?だとか…いまだにトラウマになるほど怖いです。ですが、その怖い部分に対比して、どこか暗さを喩したポップさもあり、『ゲイマンが自身の作品の児童青年文学としての応用を試みた』作風が怪しく漂います。素晴らしい”なんとか”のホラー小説です。
ゲイマンの他の作品のごとく、対象の比喩が具現化してるのですよね。だから抽象化している”もの”がどこか形を成して具現化していく様子がよく描かれていると思います。例えば、それは主人公コララインの現実の世界の父母であり、もう一つの世界における父母ですね。コララインは現実の父母に失望し、もう一つの世界における父母に魅かれる。だがその正体は罠であり、もっと良い父母を望んだ結果、間接的に生み出された、悪魔でした。評論家の中には、本書にフロイトの思想が組み込まれているといっているかたがいるようですが、たしかにその通り納得できる話です(関連リンク:(PDF) An Eye for an I: Neil Gaiman’s Coraline and Questions of Identity)。
もっともっと良いものを持ちたがるのは人間の元来の性ですが、そこでコララインにはあるべき試練があり、困難があり、なによりもそのコララインと読者に提示される謎が深まって存在するわけです。コララインは本当に大切なものを見失いがちになりますが、それは虚構への単純なあこがれに過ぎない、ということに極めて早く気付く。大切なもの、とは日常であり、普通通りに接してくれる、ちょっとばかり不満げな本来の・本当の父母です。それを我々は常々忘れがちなのですね。コララインはそこに気づく否や、すぐに行動に起こし、どのように皆を救うかといったことを考える。機転を利かせて、アイデア豊富に難局を乗り越えるわけです。ここには純粋な強い女性像があると思います。
このように本書は多面的に解釈できるものです。ホラーらしいホラー・理想に対する幻滅と希望・そして、残された謎にまつわるフロイトの悪魔…読者にこれら多様なメメントをゲイマンはこの単純な200ぺージだけの短編小説で訴えかけるわけです。あたしが考えたのは、フロイト流の精神医学ではなく、また、ホラーに対する深い考察でもありません。もうひとつ、人間の理想に対する幻滅と希望という部分です。
日常のありかたをどこに見つけ、また理想がなんたるかといったことを我々は簡単に規定しがちですが、その真意のありかたをコララインは切実に見切って行動に起こす。これはなかなか世間一般の大人でもできることではありません。騙されて、目先の利益に走ることはそれなりの代償を払う必要がある…このような単純な交換原理をコララインは行動力でもってして転覆させることができました。だからコララインは純粋な少女であり、もう大人への道を歩み始めるしっかり者なんですね。ここが切実に胸に来るものがあり、本書の残された話題の中でも唯一、いまだに泣ける部分ではないでしょうか?