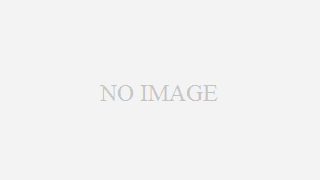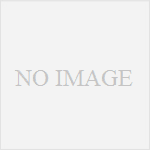記事の要約:日本の大学や大学院でゲーム研究体制が不十分だとは到底思えない。細分化しているとはいえゲームを専門とする先生が多くいるし、美大芸大のゲームコース新設のような新しい動きもある。そもそも昔からMBA/MOT分野でゲームの研究論文は数多く見受けられたし、実際ゲームは応用技術のたまものなのでとらえ方次第でどうとでもなるはずだ。語弊を承知で言えば、日本はわざわざ予算をつけて「ゲーム大国」になる必要はない。
鴨原氏のソース
「ゲーム大国」なのに研究体制が不十分な日本 留学希望者がスルーしてしまう実情(鴫原盛之) – エキスパート – Yahoo!ニュース
ライターで日本デジタルゲーム学会ゲームメディアSIG代表の鴫原盛之氏がYahoo!ニュースで2020年にまとめてますが、この論は本当でしょうか?ちょっとゲヲログ的に再解釈し、その論が正しいのかどうか検討してみようと思います。Yahoo!ニュースのソース☝です。ちなみに、このライターのかた、とても有能なかたなようでして、ゲームがらみの著書をいくつも持っている、実績のあるこの界隈ではとても有名なゲームジャーナリストなようです。
前提的結論
さて、ではどうだろうか?ぶっちゃけ、そうは思いません。実は此処ゲヲログ2.0もゲーミフィケーション分野で知識を応用活用しようという意味合いがあって運営しているのですが…あたしは、日本がゲーム大国であるのにもかかわらず、ゲーム研究の体制が不十分だ、とは思いませんね。だってゲームってあくまで応用技術の産業なんですよ。確かにゲーミフィケーションを手前味噌に掲げる大学の教員は多くはないです。でもね、ゲームそのものも、そっから始まっているゲームフィケーションそのものも基礎研究じゃないんですよね。アカデミズムでやる分野であるのか?っていうとやっぱ忌避感はあると思うんですよ。でもそれ=ゲームが盛んじゃないとか、ゲームを仕事にしにくいっていう面は全くないです。まずこの点を突き付けておきたいですね。つまり鴨原氏の意見を前提的に否定するとしたら、ここでしょう。
ゲームと応用技術は相性が良い
ゲームに必要な技術は基礎研究だけじゃなくて、むしろ応用研究であることが多い、という点。同期でも任天堂も含めてゲーム会社に就職したのはいましたが、みんなゲームサークルとかで技術を磨いて、サブドメインとしてゲームがらみの活動をやっていた人が多かったです。そういう意味ではゲームの会社に行くには大学出ておいたほうが良いんですよね。ドメイン技術としては、基礎研究分野を理系の院なりなんなりで磨いて、そっから自分で応用性をゲーム分野で開拓していった優秀なやつらが多かった記憶があります。AIの研究・システムの研究・ネットワークの研究・美術芸術表現の研究だってなんだって応用性があればゲームに行きつくことができるし、鴨原氏が執筆したのが2020年時点の記事だとしても、そうそう悲観視するのがなんだかわかりません。留学生がゲーム研究をしたくて日本に来るっていうことの生産性が、その意においてはどれほどあるのかどうかってのも疑問です。勝手にやれる分野ではあるよね、間違いなく。
日本でゲーム研究を受け入れる研究室は多い
さらに二次的に鴨原氏の意見を否定することも十分できると思います。現にかなりアカデミックではあるものの高度な研究室が多く日本にはある。同氏もソースとして出してますが、東北学院大学准教授でGLOCOM(国際大学)客員研究員の小林信重先生が日本でゲーム研究を専攻できる大学院・大学リストというページでまとめているページは有名ですね。ゲームを研究できる研究室は国際的に見て多い方だと思います。またその範囲も技術から経営までと幅が広い。有名どころだと、JAIST(北先)では基礎的なAIの研究をしてるところがあるし、むしろ東大のような超級大学でもゲーミフィケーションに近い研究まで多くやってるところは数多くある。工学から文化系の研究まで広い。これ以外にもルートは実は多く存在し、大学の学部や美術大学ではゲームのコースを作るところも増えてますし、広くとらえればMBA/MOT課程でゲームの周辺研究はできます。東京芸大だってゲームのコースは設けてるし、昔から立命館でのゲーム研究は有名です。ぶっちゃけ、数え上げたらキリがないぐらいです。
そもそもゲームはゲーム”だけ”ではない
ということで、鴨原氏の言っていることはさらに否定できると思います。最初の指摘と重なるところですが、ゲームってゲームだけでとらえちゃだめだと思うんですよ。同記事で”実情”とされ、芝浦工業大学の小山先生の言が引用されている部分によれば、『首都圏で芝浦工業大学と明治大学以外にゲーム研究を志す留学生が志望する大学はない』とのことですが、ぶっちゃけ大間違いだと思います。たしかに明治はサブカルに強いことで地味に有名です。でも、2020年の当時からゲームAIの研究をしていた大学院はJAISTの東京サテライト(社会人課程)があったし、MBA課程でも多くゲームの経営的研究を地味にしていた学生は実際あたし自身数多く見ました。当時はまだ美大芸大が主体的にゲームコースを設ける姿勢はなかったことを差し引きしても、フツーに東京工芸大学や東京工科大学がありました。ゲームがらみの研究室は事実多くあったよね、知られてないだけで。
日本は「ゲーム大国」になる必要はない
さらに、文言にあるように『日本は欧米よりも安全かつ学費が安い』というのも嘘だと思います。当然、治安が良いってのは良いことですが、それって研究をまったく関係なくね?って思う。ぶっちゃけ、別問題ですよね。欧米ではゲーム分野といえども近しい分野で研究結果さえ出せば、豊富に奨学金がもらえるはずだし、日本のほうが学費が安いってのは間違い。つか、昔から芝浦工業大学の学費は大学院であったとしても安くないです。そもそも応用産業であるゲーム分野で研究を促進して意味があるのかな?日本は日本なりにゲームに関しては研究のスタンスを構築してきたし、それは研究者の専門領域として必然だったわけで、特段問題があるとは思えません。もちろん産業として育てて、その強みを国際的に生かそうとする試みは素晴らしいですが、文意にあるような「ゲーム大国」になる必要は、2024年になった今でも日本には”ない”と思います。