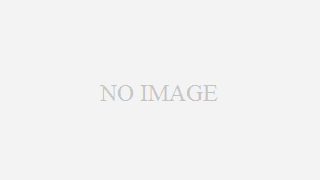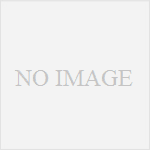ゲームという遊戯において、テレビ画面に投影される映像に反映されるレスポンスに期待をし、子供たちはこぞってコントローラーを手にとり、汗握った。ゲームは、ボタンを押すと反応が返るレスポンスの遊戯だ。子供は、ゲームは自由である、ということを信じ、それがこうしたあらゆる動きに多様な影響を及ぼすこと、幼心に確証した。そして、その上達や進展を競う分、対価として空想の中に何らかの見返りを享受することがうれしくてたまらなかったのだ。だからこそ、子供は親に叱られながらもゲームに熱中した。
当時、小学生だった我々ゲーマは大人になり、ゲームに熱中することを忘れた。残念なことに今、操作に対応するレスポンスに、過大な期待を抱くということがなくなってしまった。テレビ画面(モニター)に投影されるレスポンスの動向が、表現としてありきたりで、いかにもコンピューターによってシミュレートされているものなので、それが単調になっていることに皆飽き飽きしてしまったのだ。
ここにきて、『操作しない操作』という概念がようやっと発見された。つまり操作しないことも操作のうちに入る…ということである。音楽で言えば、休符に近い。休符という意味合いは決してその音楽の音に符号が全く存在しないことを意味するものではない。そこに”符があるかのように休符している”だけである。同じように、動くことがすべてではないのだ。つまり、動かざることで動きの意味を熟考させることがありえることが発見された。休符・後の先・剣術の型、あるいは、弓術に至るまで一貫している、いわば『残心』である。ゲームでも同じことに汎用性があること、気づいた者たちは、最初少なかったことだろう。
だが、2020年代に入り、AAA級のゲームが数多く登場した反面、従来動かさせるものが動かないことで、本来のダイナミズムを定義するゲームもまた広く発見されるに至った。その代表作が言わずと知れた「Vampire Survivors」であり、その影響を受けて作られた「Gunlocked」である。
かつて人々は、ゲームの対価としてレスポンスに期待をし、直接シミュレーション的空想上のダイナミズムに働きかけるべく、操作量を競ったが、その時代は終焉を迎えている。つまり動かさないことで、動きの動静を制御する方法を見つけたのだ。そうだ!これが「オートチェスシステム」だ。盤上に配置された休符はゲームの中毒性のあり方を変容させた。行動しない行動・行動を伴わない行動・動きがないのに動いているという状態…まさに、このことである。
あえて操作しないことで操作をする、ということはいわば、忘れられた手紙のようなものだ。ある(有)のにない(無)のだ。これは操作がない(無)のに、操作全般に影響を及ぼしている(有)ということだ。現代に至り、確実に哲学的な設計・文学的な倒置はゲームの分野でも進歩しただろう。いつかだれかがゲームで見てきた光景は時間の逆説を通じて、無限(有)と0(無)の行動哲学とつながった。
それは所詮射之射というもの、好漢いまだ不射之射を知らぬと見える。
「ああ、夫子が、――古今無双の射の名人たる夫子が、
弓を忘れ果てられたとや? ああ、弓という名も、その使い途も!」その後当分の間、邯鄲の都では、画家は絵筆を隠し、楽人は瑟の絃を断ち、
工匠は規矩を手にするのを恥じたということである。
中島敦「名人伝」より